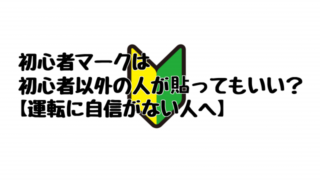法定速度と制限速度はどのように違うのか気になる方へ。
法定速度と制限速度は、単なる言葉の言い回しの違いではなく明確な違いがあります。
今回は、その違いについてわかりやすく解説をしていきたいと思います。
それでは、「「制限速度」と「法定速度」の違いをわかりやすく解説!」について書いていきます。
制限速度と法定速度はどう違うのか?
法定速度と制限速度の違いは下記のとおりです。
- 法定速度:法律で決められている最高速度
- 制限速度:標識が設置されている場合に適用される速度
法定速度は、看板のない道路に対して法律で決められている最高速度。対して制限速度は標識の速度になります。
次に、制限速度と法定速度を具体例を用いて解説していきます。
法定速度とは?
法律で定められている最高速度のことであり、道路に標識がない場合に適用される最高速度(超えてはならない速度)になります。
一般車両が定められている法定速度は、
- 一般道—時速60km
- 高速道路—時速100km
の2つの速度が法定速度となっています。
ちなみに、一般車両以外の車両に適用される法定速度は以下の通りになります。
一般道の法定速度(一般車両以外)
- 原動付き自転車:時速30km
- 緊急車両:時速80km
高速道路の法定速度(一般車両以外)
- 大型貨物・トレーラー:時速80km
- それ以外の車両:時速100km
制限速度とは?
制限速度は、速度標識が設置されている場合に適用される、最高速度のことを指しています。
よく街中で掲げられている「赤と白に青い数字」で書かれた、速度標識を目にする機会があると思いますが、
30km・40km・50km
など、守らなくてはならない制限速度が書かれています。
そのため、この標識が掲げられていない場合には、基本的に「法定速度」が適用になります。
「法定速度」は住宅地には適用されない?
実際に、住宅街など速度標識がない場合には、法定速度の60kmが合法にはなります。
しかし、住宅街のような狭い道路では、子供や自転車の飛び出しなど、予期せぬことが多く発生し、危険が伴うことが予想されます。
そのため、住宅街のような道路では、ドライバーには道路交通法第70条の「安全運転の義務」を守る必要があり、他人に危害を及ぼさない運転が求められます。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)引用元:道路交通法
スピードの出し過ぎなどにより不測の事態に対処できない運転は、スピード違反で検挙されることはなくても、「安全運転義務違反」で罰せられる可能性があること覚えておきましょう。
とはいえ、多くのドライバーは狭い住宅街の走行は警戒されていると思います。
「制限速度」と「法定速度」の違い-まとめ
本記事は、「「制限速度」と「法定速度」の違いをわかりやすく解説!」について書きました。
「制限速度と法定速度」は、言葉の違いが少しまどろっこしいですが違いがわかったのではないでしょうか?
最後に触れた住宅街など、看板の設置がない道路は、法定速度が適用されてしまいますが、道路に対して「適正な安全スピード」は存在します。
思いやりのある運転はすべての交通安全にかかわり、気持ちの良い社会が作れると思いますので、スマートなドライビングを心がけていきたいですね。