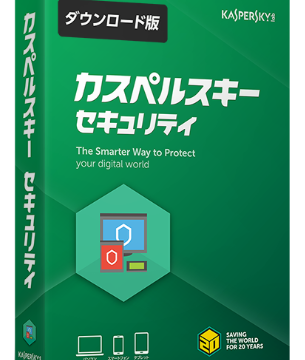冬になるとスタッドレスタイヤが欠かせない存在ですが、降雪地域に住む方でも、スタッドレスタイヤが滑りにくい理由は意外と知られていないように思います。
ゴムが柔らかい、溝が多いなどの違いは見て分かりますが意外と詳しいメカニズムは知らない方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんなスタッドレスタイヤの詳しいメカニズムについての解説になります。
そもそもなぜ「スタッドレスタイヤ」と言うのか?
もともと「スタッドタイヤ」、いわゆる「スパイクタイヤ」というものがありました。
このスパイクタイヤの金属の鋲を「スタッド」と呼び、それを無くした「レス」したことにより「スタッドレスタイヤ」と呼ばれるようになりました。
スパイクタイヤはこの「金属の鋲」で氷を引っ掻くことで主にトラクションを得ていたわけです。
しかし、積雪のない道路を走行した際にこのスタッドがアスファルトを削ってしまい、道路を傷めるだけでなく、削られてできた粉塵により、主に呼吸器疾患を起こす健康被害が発生。
法律でスパイクタイヤが禁止になったことにより「スタッドレスタイヤ」が登場しました。
でもこの「スタッドをレスした」スタッドレスタイヤはどうやって雪道で滑らないようにしているのでしょうか?
具体的に解説していきます。
スタッドレスタイヤが雪道で滑らない理由とは?
タイヤの深い溝形状に雪上性能を上げる秘密が
夏タイヤはなるべく溝を少なくすることで摩擦面を増やし、グリップ力を上げています。
それに対しスタッドレスタイヤは「深い溝」が掘られています。
雪上路面ではこの「深い溝」の中に雪を柱状に噛みこみ圧縮することで発生する粘着性能(雪柱せん断力という)によってトラクションを得ています。
またこの深い溝の形状を「角ばらせる」ことにより、深い雪の中でもより埋まりにくくなり、安定した走行を可能にしています。
【乾いた氷は滑らない】除水性能で氷上性能を確保
”乾いた氷は滑らない”横浜タイヤのアイスガードシリーズのCMでおなじみのセリフですが、氷の上で滑る要因は、氷の上に出来た薄い水の膜が原因。
そのため、スタッドレスタイヤは、タイヤのトレッド面(接地面)にぎざぎざの溝(サイプ)をつけることにより、氷の表面の水分を吸収し、氷の上を瞬間的に乾燥させることで滑りやすい氷の上でも、強力なグリップを得られるようにしています。
やわらかい”ゴムの質”を求めて各メーカーが凌ぎを削る
凍結路面というのは一見、平らにみえますが実は凹凸が激しいため、ゴムが固いと路面の凸凹に合わせて密着することが困難になってしまいます。
しかし、夏タイヤと同じゴムでは氷点下以下になるとゴムが硬化してしまいます。
そのため、スタッドレスタイヤは氷点下でもゴムの柔軟性を確保でき、かつ、ある程度暖められてもゴムが溶けださないように特殊なコンパウンドを使用しているのです。
この「低温で硬化せず、常温で溶けださないゴム」の製造は高度な技術が必要であり、
各タイヤメーカーが凌ぎを削って争っています。
最近のスタッドレスは走行性能も高い
一昔前のスタッドレスは夏タイヤと比べるとドライ路面で腰砕け間や高速走行時に不安定に
なったり、ロードノイズが大きかったりといった弱点が存在していました。
しかし、最近のスタッドレスタイヤは技術の進歩により、国産メーカーであれば
軒並み走行安定性・操縦性、はたまたロードノイズも夏タイヤと遜色ないレベルに高まっています。
技術の進歩はすごい・・・
しかしスタッドレスを履いたからといって過信は禁物

一見万能と思われがちなスタッドレスタイヤですが、苦手なシチュエーションも存在します。
例えば、氷点下でクルマが何十台も通ることで磨かれたツルツルの「ミラーバーン」が日中に溶かされた場合。
雪が解けて、氷の上に水がのった状態になると、サイプの吸水性能が追い付かなくなり、非常に効きにくくなります。
「ブラックアイスバーン」や「ミラーバーン」などのツルツルに磨かれた路面では特に
細心の注意を払って、走行が必要となります。
また、スタッドレスは経年劣化や走行による摩耗により性能低下を起こします。
安全に走行するためにも、スタッドレスタイヤの寿命にも注意しなければなりません。

まとめ
いかがでしたでしょうか?
スタッドレスタイヤが滑らない理由を4行で解説すると
- 深い溝が雪をガッチリキャッチ
- サイプによる除水性能により氷を乾かす
- 低温でも硬くならない特殊コンパウンドの使用
- でも限界もあるので過信は禁物
最近のスタッドレスは雪上だけでなく、雪のないドライ路面でも走行性能が高いので雪の少ない地域でも予防的に履くことができるのでいいですよね。
毎年おすすめのタイヤ銘柄は変わりますが、以下の記事で今年度のコスパ最強銘柄を紹介してますのでスタッドレスの購入を検討している方は、あわせて読んでみて下さいね。