ディーゼルエンジンは「トルクフル」「燃費も良し」「燃料代安い」「リセールバリューも良い」と話題であり、人気が高まってきています。
しかし、このディーゼル機関に使われる軽油。
実は、冬期は凍結に気をつけなければならないのはご存知でしょうか?
特に都会から寒冷地にレジャーや帰省で行く方は、知らないと大変なことになってしまうかもしれないのでぜひお読みいただければと思います。
軽油は凍結する!?軽油は凍る軽油と凍りにくい軽油がある
軽油が凍るというのは燃料の流動性が落ち、燃料系を目詰まりさせることで起きてしまいます。
そして、軽油はJIS規格に定められた特1~特3号と5段階の種類があり、「流動性」と「目詰まり点」を添加剤により調整しているそうです。
- 特1号 流動点 +5 ℃以下 目詰まり点 –
- 1号 流動点 -2.5℃以下 目詰まり点 -1℃以下
- 2号 流動点 -7.5℃以下 目詰まり点 -5℃以下
- 3号 流動点 – 20℃以下 目詰まり点 -12以下
- 特3号 流動点 – 30℃以下 目詰まり点 -19以下
(注)JIS規格から一部抜粋
一般的に冬期(12月~3月)に販売されている軽油は2~3号で、気温が著しく低い北海道の道南以外の地域では凍りにくい特3号が販売されているようです。
これはJISのガイドラインにより、地域および月ごとに推奨する軽油の種類が指定されています。
- 3号軽油
12月 北海道全域、中部山岳地方
1月~3月 北海道道南、中部山岳地方、東北 - 特3号軽油
1月~3月 北海道(道南を除く)※同じ地域でも都市部と山間部で違うこともある。
(注)JIS規格から一部抜粋
このことから寒冷地の軽油は、凍結しにくいということがわかると思います。
ちなみにガソリン(レギュラー・ハイオク)は凍結することはありませんので安心してください。
軽油を凍結防止するには寒冷地で給油しよう
凍結を防止する具体的な方法は「寒冷地のガソリンスタンドでなるべく多めに給油」すること。
そのため、最低でも現地で半分以上給油できるように計算して出発できるようにしましょう。
できるだけ寒冷地で給油できる「3号以上」の軽油に置き換えるのが望ましいですが、ガス欠を起こすと元も子もありません。
ギリギリまで粘らずに適度なところで給油しましょう。
燃料タンク内の3号軽油の比率が高くなれば、軽油は目詰まりしにくくなります。
また、寒冷地で2号以下の軽油を使用していてもエンジンが動いている時は凍結することはないので、必要以上に焦る必要はないということも付け加えさせてください。
もし軽油が凍結してしまったら・・・
気温の上昇を待ち、エンジンがかかるようになってから最寄りのSSで給油するか、JAFを呼んで救援してもらいましょう。
燃料フィルター付近や燃料が通る配管を温める手段もありますが、シロウトがその場で行うよりも、知識・経験豊富なJAF隊員に作業を行ってもらう方が確実といえます。
解凍できなかった場合には、レッカーで整備環境の整った場所まで運んでもらえますので安心できるでしょう。
JAFに加入するには年会費4,000円がかかりますが、安心のための保険となるだけでなく、JAF会員は各地で優待割引が受けられます。
もし「加入してないよ!」という方がいましたら、元を取ることも可能なので加入をおすすめします。
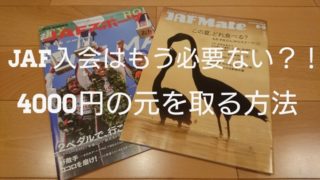
まとめ:軽油は凍結する可能性があるので注意しよう
- 冬季の寒冷地では3号以上の凍りにくい軽油が使用されている。
- 非寒冷地から寒冷地へ行くときは、寒冷地で1/2以上給油できるように調整する。
- エンジン始動時にはまず凍結はしない。
- 万が一凍結したらJAFを呼ぶ。
ディーゼル車で寒冷地へ行く際は、トラブルに見舞われないためにも給油するタイミングを気にかけていただくことが大事だといえるでしょう。
是非参考にしていただき、快適な旅を過ごしてくださいね!












